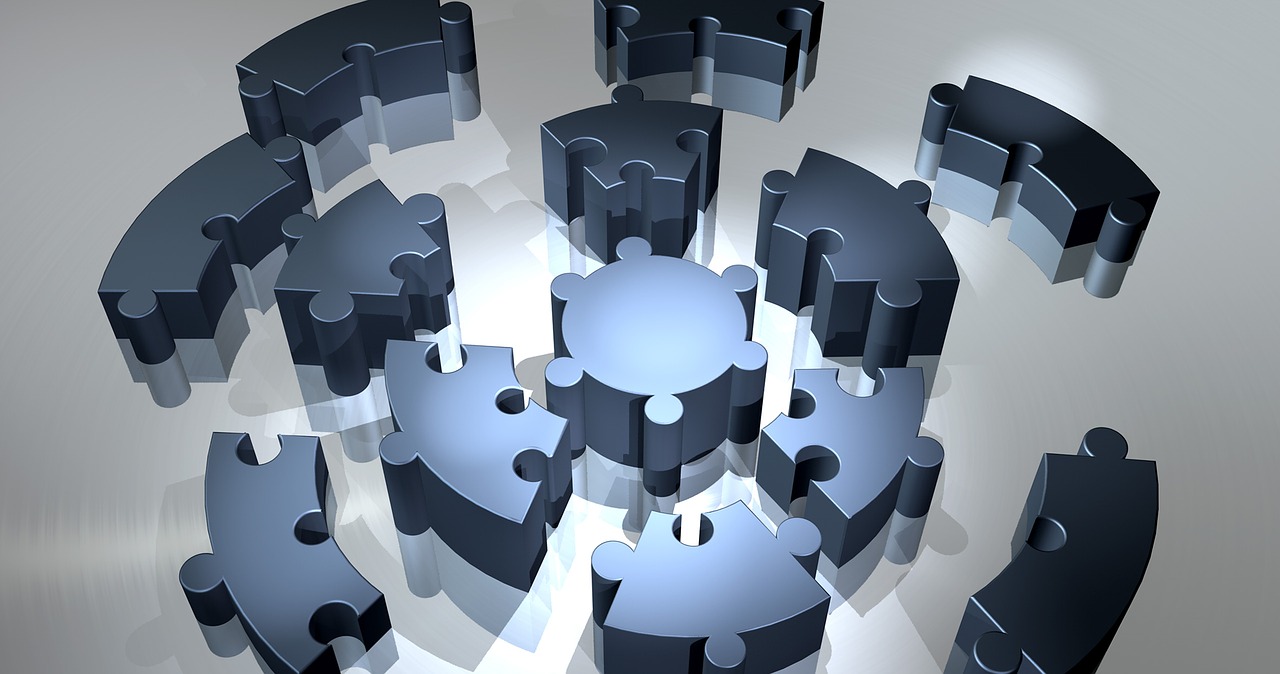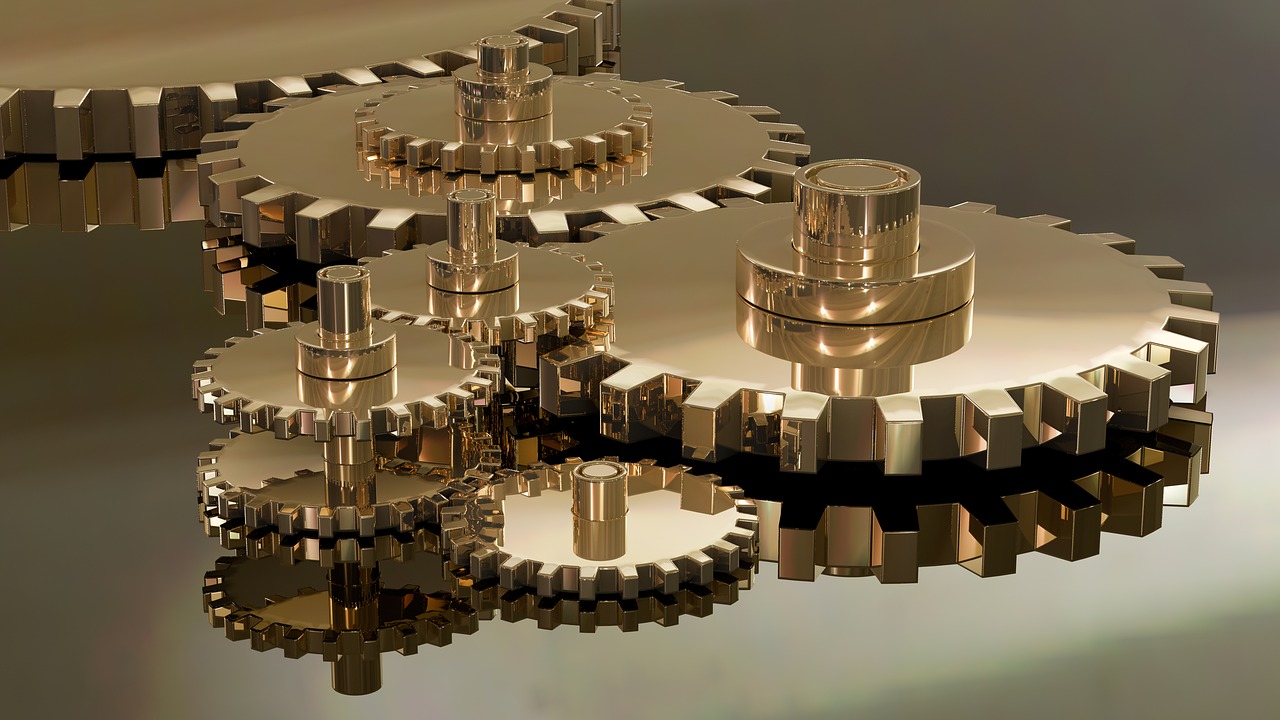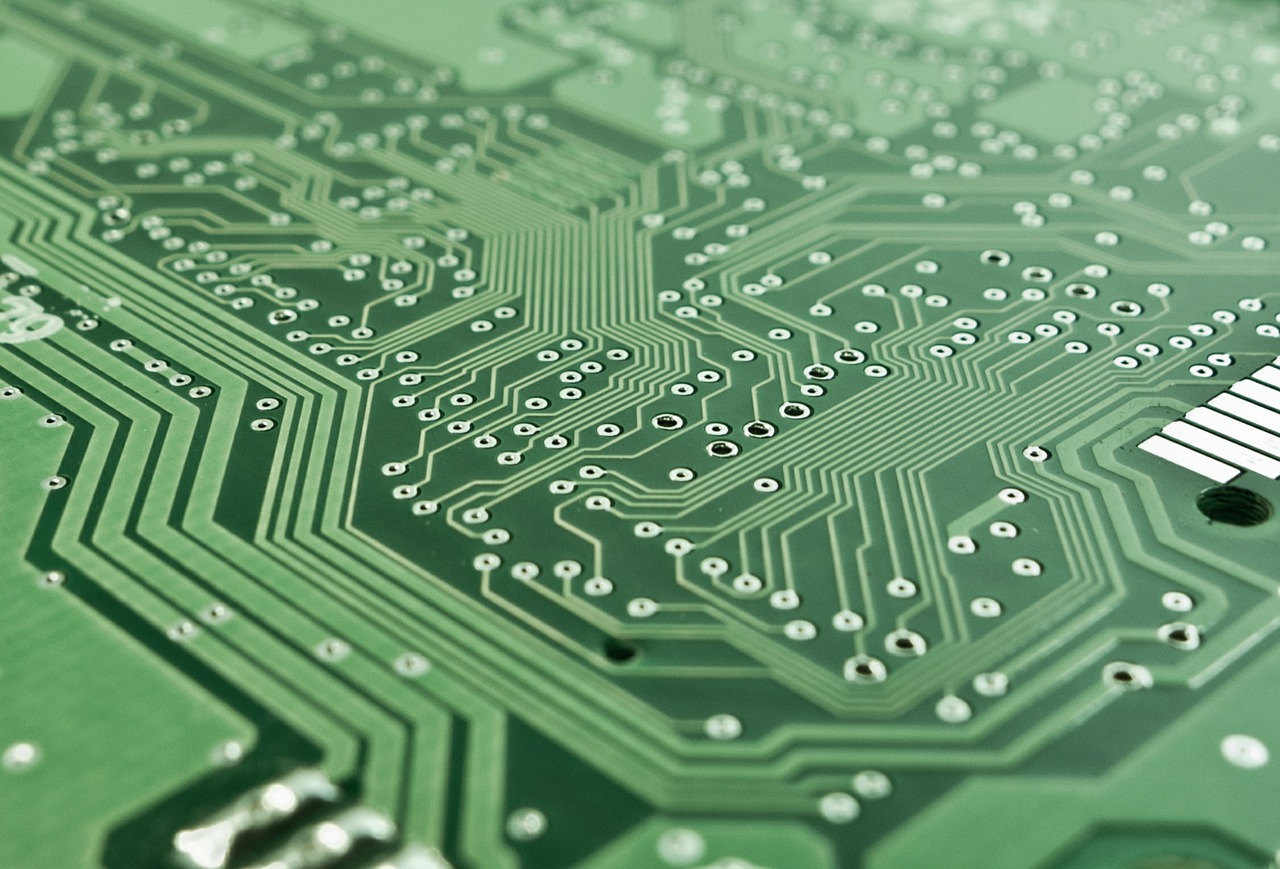IT大国として知られるインドでは仮想通貨やブロックチェーン学習にも積極的です。
2019年5月には国立のビジネススクールである「インド経営大学院(IIMs)」のカルカッタ校で仮想通貨に関連した教育プログラム「フィンテックと金融ブロックチェーンの上級プログラム(APFFB)」が開始されました。
そんなインドでの仮想通貨の規制状況は複雑なことになっています。
インドの仮想通貨の規制当局とは

インドで仮想通貨はインド国内での通貨の定義を満たしていないとして、法的な位置付けが定められていません。
そのため規制当局としてインド証券取引委員会(Securities and Exchange Board of India, SEBI)とインド準備銀行(Reserve Bank of India, RBI)が別々に活動しています。
SEBIは1992年に設立された機関で、証券取引市場の規制や不正調査を通じて市場の発展や投資家の保護を目指しています。
インドで最も重要な規制当局のひとつで、投資家からの信用も厚いです。
一方RBIはインドの中央銀行です。
貨幣の発行のほか金融機関に働きかけ、インド国民が円滑な金融サービスを享受できるよう働きかける仕事もしています。
インドでは2005年時点で国民の59%しか銀行口座を開設できていないというデータがあり、金融包摂が国の大きな課題となっていました。
インドでの仮想通貨への規制状況

SEBIは仮想通貨の規制に前向きな姿勢を示しており、2017-2018の年次報告書においてスイス、イギリス、日本に職員を派遣したことを明らかにしています。
仮想通貨の取引が盛んに行われており、規制も整備された国々の方針を学ぶことで、SEBIでの仮想通貨規制法案作りの参考にしようとしているようです。
ですが2018年4月にはRBIがすべての金融機関の仮想通貨、および仮想通貨の処理を補助するようなサービスの取り扱いを禁止しました。
このRBIの決定はインドでの仮想通貨取引に大きな影響を与え、2018年9月にはインド最大の仮想通貨取引所であるZebpayが国内向けのサービスを停止しました。
同様の事情でCoinDeskやCoinomeといった取引所がインド向けのサービスを停止しています。
インド最高裁判所にはRBIの決定を取り下げるような申請が何度も行われましたが、いずれも無駄に終わっています。
2019年4月にはインド国内での仮想通貨を禁止する草案が出回るなど、インドでの仮想通貨規制を巡る動きは混迷しています。
なぜインドでの仮想通貨規制は揺れるのか

インドで仮想通貨規制の方針が定まらないのは、規制当局がSEBIとRBIの2つ存在することです。
仮想通貨の定義が定まっていないうえ、金融規制も分業が進んでいるため、複数の機関が仮想通貨に対する権限を持つという事態を招いています。
日本では金融庁、アメリカではSECと、仮想通貨規制の進む国では、仮想通貨分野を含む金融市場の広い範囲を統括する機関が存在しています。
インドで仮想通貨を規制するうえには仮想通貨の定義に加え、現在の機関の構成も再考する必要があるでしょう。